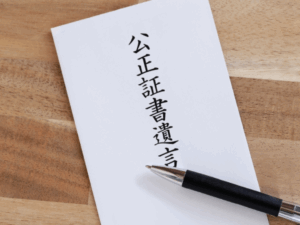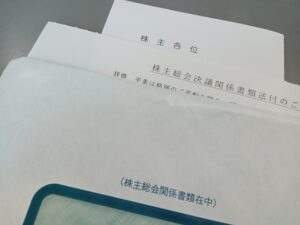【2026年1月施行】改正行政書士法のポイントを徹底解説!

2025年6月に「行政書士法の一部を改正する法律案」が成立しました。
2026年1月1日に施行される改正行政書士法では、特定行政書士の業務範囲の拡大や業務の制限規定の趣旨の明確化など、5つの点で改正が行われます。このうち、ポイントになるのが業務の制限規定の趣旨の明確化です。これにより、無資格者による補助金申請代行への取り締まりが大幅に進むと考えられています。
本記事では、そんな改正行政書士法のポイントを5つに分けて解説します。行政書士法の定義や、改正行政書士法の施行がもたらす影響についても解説するため、ぜひ参考にしてください。
行政書士法とは
行政書士法とは、資格要件や業務の範囲、目的、義務など、行政書士の制度について規定した法律です。
たとえば、第1条(目的)には、次のように目的が明記されています。
| 第一条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。 |
出典:e-GOV法令検索「行政書士法」
このように、行政書士法では、行政書士が守るべき条文が記載されています。
改正行政書士法はいつ施行される?
改正行政書士法は、2026年1月1日に施行されます。
ちなみに、衆議院を可決したのは2025年5月30日、参議院を可決したのは2025年6月6日です。
行政書士法が改正される背景
行政書士法が改正される背景には、まず社会のデジタル化や制度の複雑化により、専門的な支援ニーズが高まったことがあります。
行政書士法の改正をを後押ししたのは、専門的な支援ニーズの高まりだけではありません。「報酬を得て官公署に提出する書類を作成できるのは行政書士のみ」と規定されていたにもかかわらず、無資格の事業者による無責任な業務介入(闇コンサル)が増えていたことも、法改正のきっかけになったとされています。無資格の事業者による業務は、依頼者の不利益につながるケースが少なくなく、行政書士業界の健全な発展を阻害する要因になっていたためです。
こうした背景を踏まえ、依頼者が安心して法務サービスを利用できるようにするとともに、行政書士の職域が不当に侵害されることがないよう、行政書士法が改正されることになりました。
改正行政書士法の5つのポイント

改正行政書士法のポイントは、次の5つです。
- 行政書士の使命の明確化
- 職責の新設とデジタル社会への対応
- 特定行政書士の業務範囲の拡大
- 業務の制限規定の趣旨の明確化
- 両罰規定の整備・強化
それぞれのポイントを解説するため、ぜひ参考にしてください。
行政書士の使命の明確化
改正法では、行政書士の社会的責任について、「国民の権利利益の実現に資する」という使命が明記されます。
これまで、弁護士や司法書士、社労士などの他士業では、使命が法律に明記されていた一方、行政書士には、使命の規定がありませんでした。しかし、法改正により、「目的」という表現から「使命」へと変更され、行政書士が果たすべき役割がより明確になります。
| (行政書士の使命) 第一条 行政書士は、その業務を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを使命とする。 |
出典:日本行政書士会連合会「行政書士法の一部を改正する法律案 新旧対照表」
職責の新設とデジタル社会への対応
改正法では、行政書士の職責が新たに明記されます。
具体的な職責については、まず行政書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令と実務に精通して、公正かつ誠実に業務を行わなければなりません。
そのうえで、行政書士は、業務推進にあたり、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取り組みを通じて、国民の利便の向上と業務の改善進歩を図るよう努める義務を負います。
デジタル社会への対応の努力義務については、社会のデジタル化が進むなか、士業法で初めて規定されました。
| (職責) 第一条の二 行政書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。 2 行政書士は、その業務を行うに当たっては、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び当該業務の改善進歩を図るよう努めなければならない。 |
出典:日本行政書士会連合会「行政書士法の一部を改正する法律案 新旧対照表」
特定行政書士の業務範囲の拡大
改正法では、行政書士が作成できる書類であれば、実際に作成していなくても、不服申立ての代理ができるようになります。
現行法では、行政書士が作成した書類しか不服申立ての代理ができません。しかし、法改正により、行政書士の前段階関与のない書類の不服申立ての手続きも代理することが可能になります。
| 第一条の四 二 前条の規定により行政書士が作成することはできる官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。 |
出典:日本行政書士会連合会「行政書士法の一部を改正する法律案 新旧対照表」
業務の制限規定の趣旨の明確化
改正法では、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が追記され、業務の制限規定の趣旨が明確化されます。
これにより、どのような名目であっても、行政書士以外が報酬を受け取り、官公署に提出する書類等を作成することが禁じられます。
総務省は、これまで補助金の申請書作成業務を行政書士の独占業務とすると明言していました。つまり、今回の法改正により、補助金の申請書作成業務が行政書士の独占業務になるといえます。
| (業務の制限) 第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。 |
出典:日本行政書士会連合会「行政書士法の一部を改正する法律案 新旧対照表」
両罰規定の強化
改正法では、行政書士法人の社員が法律違反をした場合、本人に加えて法人も責任を問われる両罰規定が強化されます。
現行法では、「調査記録簿の記載等」に関してのみ両罰規定が明記されています。しかし、法改正により、両罰規定の範囲が、「無資格者による業務の制限」や、「名称の使用制限」まで広がります。また、行政書士法人の帳簿備え付け・保存義務違反、依頼に応じる義務違反、都道府県知事による立ち入り検査の拒否・妨害・忌避といった行為も罰則対象になります。
| 第二十三条の三 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前条第一号の二、第二十二条の四、第二十三条第二項又は前条の違法行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 |
出典:日本行政書士会連合会「行政書士法の一部を改正する法律案 新旧対照表」
改正行政書士法の施行が与える影響
改正行政書士法の施行が与える影響には、次の2つがあります。
- 補助金申請代行への取り締まりが進む
- 各専門職間で業務範囲の線引きが明確になる
無資格者による補助金申請代行への取り締まりが進む
法改正により、無資格者による補助金申請代行への取り締まりが進むと考えられます。前述のとおり、業務の制限規定の趣旨の明確化により、無資格者が報酬を得て行政書士業務を行うことへの規制が強化されるためです。
取り締まりが進むのは、補助金申請代行に対してだけではありません。在留資格関連では、登録支援機関による特定技能の書類の作成や入管への取り次ぎ申請が実質的な無資格業務とみなされ、罰則の対象になる可能性があるでしょう。
各専門職間で業務範囲の線引きが明確になる
法改正により、行政書士の業務独占規定が明確化されたことで、今後、中小企業診断士や税理士など、各専門職間で業務範囲の線引きがより明確になると考えられます。
つまり、法改正後は、今まで以上に各専門家が専門性を生かし、定められた業務範囲を遵守することが求められるといえるでしょう。
松江市で、補助金申請をご検討の方は行政書士にご相談ください
改正行政書士法の施行により、、無資格業者による補助金申請代行業務は法人、個人を問わず、違法行為になります。したがって、これまで無資格業者に補助金申請代行を依頼していた方は、行政書士に申請代行業務を依頼されることをおすすめします。
小村渉行政書士事務所では、補助金申請代行を専門にしています。松江市で、補助金申請をご検討の方は、当事務所にご相談ください。