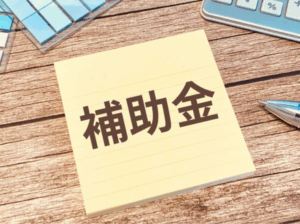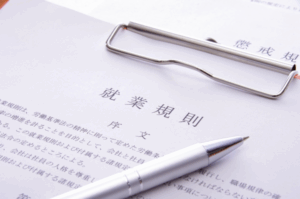自筆証書遺言の法律上の要件とは?作成する際のポイントも解説!

出典:photoAC
自筆証書遺言は、遺言者が全文を自筆で書く遺言書です。2020年から、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度が始まったこともあり、関心を持つ方も増えていますが、民法では、厳格な要件が定められており、要件を満たさない遺言書は、無効になるおそれがあります。
これを踏まえ、本記事では、自筆証書遺言の法律上の要件について解説します。自筆証書遺言を作成する際のポイントについても解説するため、ぜひ参考にしてください。
自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言は、遺言者自らが、遺言の全文、日付、氏名を自書したうえで、押印する遺言書です。
自筆証書遺言は、費用がかからず、いつでも手軽に書き直すのがメリットです。また、遺言者は遺言の内容を自分以外に秘密にできます。
一方、自筆証書遺言は一定の要件を満たしていないと無効になるおそれがあります。また、遺言書自体が紛失したり、存在自体を忘れ去られたりする場合があります。また、遺言者が自書して作成することから、改ざんリスクもゼロではありません。
こうしたリスクにより、民法では、自筆証書遺言の法律上の要件が厳格に定められています。
自筆証書遺言の法律上の要件
自筆証書遺言の法律上の要件は次の5つです。
- 遺言者本人が自筆で全文を書く
- 日付を自書する
- 氏名を自書する
- 押印する
- 訂正のルール守る
ここからは、それぞれの要件について解説します。ぜひ参考にしてください。
遺言者本人が自筆で全文を書く
自筆証書遺言では、遺言者が財産目録以外の部分を自筆で作成しなければなりません。第三者による不正や偽造を防ぐためです。
もし家族など本人以外の者が代筆したり、遺言者がパソコンで記入したりすれば、その自筆証書遺言は無効となります。
民法改正に伴い、2019年1月13日から財産目録については、パソコンや代筆で作成できるようになりました。ただし、自筆以外の財産目録を添付する場合は、すべてのページに署名押印する必要があります。
日付を自書する
自筆証書遺言書には、作成した日付を正確に書かなければなりません。遺言者に遺言を作成する能力があったかどうか(遺言能力の有無)を判定する際に、作成した日付が重要になるためです。また、遺言者が複数存在する場合に新しい日付の遺言書が法的に有効となるルールに照らし合わせ、複数の遺言書がある場合、作成の先後を確認する際に作成した日付がその判断基準となります。
日付の記載する際は、元号を使っても西暦を使っても構いませんが、年月だけで日にちの記載がない遺言は日付が特定できないため、無効となります。また、「吉日」などと記載した遺言も、日付を特定できないため、無効です。
氏名を自書する
自筆証書遺言では、遺言者が戸籍上の氏名を自筆で正確に記載する必要があります。氏名の自書は、遺言作成者が誰なのか、遺言作成者本人が作成したものであることを明らかにするために要求されるためです。
法的な要件ではないものの、より正確に人物を特定するため、名前の前に住所を記載するのが望ましいとされます。
押印する
自筆証書遺言では、遺言者は、名前の後に実印で押印しなければなりません。
押印は認印でも構いませんが、実印のほうが、遺言者本人による執筆がより明確に証明でき、トラブル防止にもつながります。 また、自筆証書遺言を長期間保存するケースを想定する場合は、インク式よりも、朱肉式の印鑑を使用するのがおすすめです。
訂正のルールを遵守する
自筆証書遺言では、訂正する場合は遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければなりません(民法968条2項)。この方式に則って訂正しなければ、その部分が無効となります。
このように自筆証書遺言を訂正する際は手順が多いことから、訂正箇所が多い場合は最初から書き直すことをおすすめします。
自筆証書遺言を作成する際のポイント
自筆証書遺言を作成する際は、次のポイントを抑えることが大切です。
- 誰にどの財産を相続させるのかを明記する
- 共同遺言による遺言の無効化に注意する
- 曖昧な表現を避ける
- 認知能力があるうちに作成する
これらのポイントを押さえることで、精度の高い自筆証書遺言を作成可能です。ぜひ参考にしてください。
誰にどの財産を相続させるのかを明示する
自筆証書遺言は、誰にどの財産を相続させるのかをしっかり明示する必要があります。曖昧な表現だと、相続人間でトラブルに発展する可能性があるためです。
たとえば、「金融資産一千万円を3兄弟で3分割して相続し、残余財産はすべて妻に相続させる」と書いたとします。このような書き方では、金融資産に証券や株が含まれていると、資産の分割方法が無数にあるため、トラブルの原因になりかねません。
したがって、自筆証書遺言では、誰に、どの財産を、どのように遺すかを明記することが大切です。たとえば、Aには、「●株式会社の株式 数量◯株」、Bには、「◯銀行◯支店 普通預金口座番号◯◯◯◯」など、誰が見てもわかるように記載しましょう。
共同遺言による遺言の無効化に注意する
自筆証書遺言を記載する際は、共同遺言による遺言の無効化に注意してください。民法975条で、「遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない」と記載されているように、共同遺言が禁止されているためです。
遺言書は各自がひとりで、自分の分を執筆することを念頭におきましょう。
曖昧な表現を避ける
自筆証書遺言を作成する際は、曖昧な表現を避けましょう。読み手の解釈が分かれるような曖昧な表現で文言を記載すると、遺言の解釈を巡って訴訟に発展するリスクがあるためです。
たとえば、自筆証書遺言内で、「自宅は長男に譲る」と書いても、自宅という表記では、第三者が不動産を特定できません。そのため、法務局が相続登記を受理してくれないという問題が生じるほか、当該部分が無効になる可能性もあります。
このような問題が生じないように、土地や建物は地番や家屋番号などの所在地、金融資産については取引銀行や口座番号を記載したうえで、「取得させる」「第三者に遺贈する」「相続させる」という明確な表現を用いることが重要です。逆に、「任せる」「譲る」「託す」といった表現は、誤解を招くので書かないようにしましょう。
認知能力があるうちに作成する
自筆証書遺言は、遺言者が認知能力があるうちに作成しましょう。自筆証書遺言に限らず、遺言者は、作成時に遺言能力がなければ、無効になるためです。
遺言能力は、遺言者自らが遺言の内容とその結果を理解し判断できる能力のことです。この遺言能力がない状態、たとえば認知症や重度の精神疾患を患っている状態で作成された遺言書は、無効になるおそれがあります。
松江市で自筆証書遺言の作成でお悩みの方は行政書士事務所にご相談ください
自筆証書遺言を作成しても形式の不備や表現の問題によって、遺言書が無効になったり、トラブルにつながったりするリスクがあります。
遺産相続では複雑な事情があり、どんな遺言書を作成すればよいか迷う方も多いでしょう。自筆証書遺言の作成方法でわからないことがあれば、行政書士にご相談ください。行政書士は、法的に問題のない自筆証書遺言の作成を筆頭に、相続に関するお困り事に全力で対応いたします。