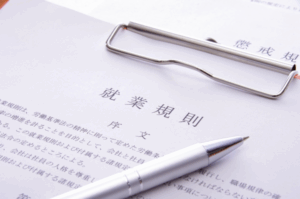10月1日からウェブ会議で公正証書遺言の作成が可能に!
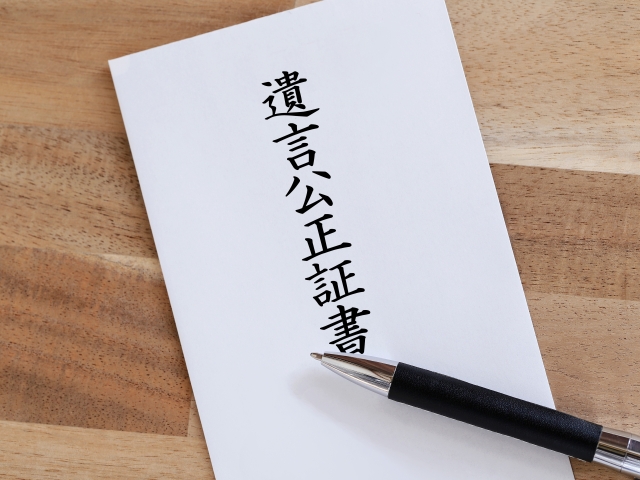
改正公証人法の施行により、2025年10月1日より公正証書がデジタル化され、それに伴いウェブ会議で公正証書の遺言で作成できるようになります。本記事では、法改正のポイントについて解説します。
現在の公正証書遺言の作成方法

現在は、遺言者本人が公証役場を訪れなければなりません。訪問後は、公証人に対し、証人2名の前で、遺言の内容を口頭で説明します。
遺言者の説明を受けて、公証人は、遺言者の遺言能力の有無や遺言者の意思に沿ったものであるかなどについて、確認します。遺言の内容に間違いがない場合、遺言者と証人2名、公証人が遺言公正証書の原本に署名、押印することで、遺言公正証書が完成します。
改正公証人法のポイント
2025年10月1日に施行される改正公証人法のポイントは、次の3つです。
- インターネットによる嘱託
これまで遺言者等は公証役場に訪れて印鑑証明書等の書面により本人確認する必要がありました。
施行後は、遺言書等が電子データに電子署名、電子証明書を添付したメールを公証役場に送付することで、電子的に本人確認することが可能になります。
- ウェブ会議の利用(リモート方式)
これまで遺言者等は原則として公証役場で公証人と対面して公正証書遺言をはじめとした公正証書を作成する必要がありました。
施行後は、遺言者等が公証役場の外からウェブ会議に参加して公正証書を作成できるようになります。
- 電子データでの作成
施行後、公正証書は、原則として電子データで作成・保存されることになります。公正証書の電子化に伴い変更点は次のとおりです。
| 紙媒体の場合 | 電子データの場合 | |
| 嘱託人 | 署名押印が必要 | 電子サインでOK(押印不要) |
| 公証人 | 署名押印が必要 | 電子サインと電子署名 |
出典:日本公証人連合会「公正証書の作成手続がデジタル化されます!」
ただし、公正証書に記録された事項の証明情報(正本・謄抄本)は電子データでの発行・交付、紙の書面での発行・交付のいずれもが可能になります。
リモート方式による公正証書遺言の作成手続きの流れ
リモートによる公正証書遺言の作成手続きの流れは次のとおりです。
- 遺言者と証人がウェブ会議招待メールよりウェブ会議に参加
- 公証人が遺言者と証人の本人確認・意思確認
- 公証人が画面に表示された公正証書遺言案を読み上げ、遺言者と証人が内容を確認
- 公証人が遺言者と証人に対し、公正証書遺言案を記録したPDFファイルへの電子サインをメールで依頼
- メールを受信した遺言者と証人が電子サインを実施・送信
- 公証人が電子サイン・電子署名
現行方式と比較して承認・確認フローに大きな変化はありませんが、すべてリモートで完結している点で大きく異なるといえます。
リモート方式利用の要件
公正証書遺言の作成にあたり、遺言者がリモート方式を利用するためには、次の要件を満たす必要があります。
- 嘱託人(遺言者や証人等)または代理人によるリモート方式利用の申し出があること
- 嘱託人・代理人のリモート参加について、ほかの嘱託人に異議がないこと
- 公証人が嘱託人・代理人のリモート参加を相当と認めること
3つの要件のうち、ポイントになるのが、「公証人がリモート参加を相当と認めた場合である」という要件です。この要件を充足しているかどうかは、リモートでの本人確認や真意の確認、判断能力の確認のしやすさなどを総合的に考慮して判断されます。
つまり、リモート方式での公正証書遺言の作成が認められるかどうかは、公証人の裁量にかかっている点に留意する必要があるでしょう。
松江市で公正証書遺言の作成をご希望の方は行政書士のご相談ください
ウェブ会議を通じて公正証書遺言の作成が可能になる改正公証人法の施行は、これまで物理的に遠いといった理由から、公正証書遺言の作成が難しかった人にとって、メリットの多い法改正といえます。
しかし、本人確認や真意確認の重要性は、現行制度と比べて変化するわけではありません。むしろ従来以上に重視される可能性があります。
このように改正公証人法の施行には留意点が多数あるため、ウェブ会議を通じて公正証書遺言の作成をご検討されている方は、行政書士にご相談ください。